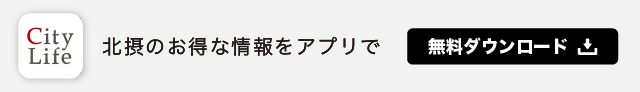「教科書通りに進むのではなく、子どもの発想を大事にしてくれる」。そう話すのは、小学1年生のときから通うMちゃんのお母さんOさん。「先生は、子どもの“これがしたい!”という思いを大事にしてくれます。それを形にしていくのがプログラミングなんだと言ってくれます」。子どもの自主性を大切にする学びのスタイルはMちゃんを大きく変えた。「いろんなことに対して自信をもつようになりました。それが学ぶ意欲につながって、学校や塾の勉強も自分で目標を立てて取り組むようになっています」。最近ではOさんが製作するジュエリーを紹介するため、オリジナルのウェブサイトを作ってくれたそう。将来は「誰もしたことがない仕事がしたい」と話しているそう。